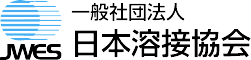新エネルギー源とその実現に向けた製造技術の展望(2025/11/27開催)
2025年8月8日公開
(第11回溶接・接合プロセス研究委員会主催シンポジウム)
開催趣旨
我が国では化石燃料への過度な依存から脱却し,エネルギー危機にも耐え得る需給構造への転換を図るため,徹底した省エネルギーへの取り組みとともに,エネルギー源の多様化に向けて様々な検討が積極的に推進されている。また,スマートフォンやタブレットなどの電子デバイスが急速に普及し,今やライフラインとも言える状況の中,さらにDXやAI活用の進展による電力需要の増大が想定される中でGXへの対応も求められることから,新エネルギー源の具現化は,最早喫緊の課題といえる.このような状況において,エネルギー源の開発に関わる様々な製造業における最先端のものづくりを支える基盤技術としての溶接・接合技術においても,さらなる高度化と高信頼性化が求められている.
以上のような背景の下,当委員会ではエネルギー源の多様化とGXを実現するとともに産業競争力向上も具現化すべく様々な技術開発が試みられている新エネルギー源に関わる製造分野における取り組みに焦点をあてました。本シンポジウムでは,発電技術を中心とした新エネルギー源の開発に関わる研究者・技術者の皆様を講師に迎え,我が国におけるエネルギーの安定供給に向けた研究・開発に関する最新情報をご紹介させていただく機会として企画させていただきました.さらに,講師の皆様を含む参加者全員で,エネルギー需給に対する将来展望についてディスカッションさせていただく機会にしたいと存じます.今回の企画が皆様にとって新たな情報の共有と有意義な議論の場となれば幸いです.
開催要領
| 1.開催日 | 2025年11月27日(木) 10:00~17:00(開場09:30) |
| 2.会 場 | (一社)日本溶接協会 溶接会館2Fホール/WEB会場 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 |
| 3.定 員 | 溶接会館 :70名 ※先着により締切り,都合による変更有 WEB会場 :100名 |
| 4.受講料 | 協会会員:18,000円 (日本溶接協会 会員会社) 後援会員:21,000円 (後援団体・指定機関 会員会社) 一 般:26,000円 (上記以外) ※受講料区分の詳細は、「申込方法他」をご確認下さい. ※上記金額は消費税を含みます.現地,WEBでの受講料に差異はありません. |
プログラム
| ①火力発電の現状および将来と溶接技術 東芝エネルギーシステムズ(株) 藤田 善宏 氏 脱炭素化に向けて,火力発電もより一層の高効率化が進んでいる.高効率化するにつれて,蒸気温度も上昇し,それに伴い,適用される材料も耐熱材料が増えている.このため,これら材料の溶接技術もより高度な技術が求められる.本発表では,溶接技術を中心に,火力発電で適用される製造技術を紹介する. |
| ②アンモニアによるエネルギー転換 (株)IHI 藤森 俊郎 氏 アンモニアは,燃焼により二酸化炭素を排出せず,水素エネルギーの優れた輸送・貯蔵特性から,脱炭素社会に向けたエネルギーとして,注目されている.IHI は,製造から利用までのアンモニアバリューチェーンの構築に向けた技術,事業開発を進めており,社会実装段階にあるガスタービン,ボイラ,内燃機関の発電・動力技術や周辺技術について現状と展望を紹介する. |
| ③次世代革新炉開発の取組みと原子力を支える溶接技術 三菱重工業(株) 下楠 善昭 氏 原子力発電は,第7次エネルギー基本計画にて最大限活用の方針が示され,より安全性を高めた新型炉の開発が期待されている.本講演では,三菱重工業における次期プラントに向けた革新軽水炉の開発,さらには多様化するニーズに対応した高速炉,高温ガス炉,小型炉および核融合炉開発の取組み状況とともに,原子力機器の製造を支える溶接技術について紹介する. |
| ④核融合炉における接合技術課題 量子科学技術研究開発機構 谷川 博康 氏 重水素―三重水素核融合反応によるエネルギー生成を目指す磁場閉じ込め型核融合炉では,炉内機器はプラズマからの熱負荷だけでなく,核融合反応によって生じる高エネルギー中性子の照射を,強磁場下で受けるという極限の複合環境下で使用される.本発表では,これらの炉内機器における溶接・接合技術の現状と今後の課題について概説する.また,フランスで建設が進められているITERにおける溶接技術に関する話題にも触れる. |
| ⑤航空機産業の挑戦と先進材料・製造技術開発の展望 川崎重工業(株) 都筑 亮一 氏 世界の航空機産業では,省エネルギーと脱炭素の取り組みなど,社会経済システムを変革させ,持続可能な成長を目指す活動の一環として機体・エンジン分野で鋭意開発を進めている.本講演では,機体・エンジンの開発動向と,現在の航空機で使用されている材料・溶接接合技術の概要,そして先進材料開発・製造技術開発の展望を紹介する. |
| ⑥定置用大型リチウム二次電池への期待と課題 -安全性評価と国際標準化- 一般財団法人 電気安全環境研究所 本多 啓三 氏 再エネのさらなる増強に向けて導入拡大が期待されているリチウム二次電池においては,安全性の確保が最重要課題である.ここでは,電池の安全性評価法として注目されているレーザ照射による類焼試験法(熱連鎖試験)とその国際標準化の状況を紹介する.また電池の劣化に伴い安全性が低下する現象を把握する評価法としてもレーザ照射法が有効であることを解説する. |
申込方法他
(1)お申込はWEB専用となります(日本溶接協会ホームページトップでご案内).
(2)申込締切は,11月21日(金)とします。
※不明な点はパンフレットに記載の事務局メールへご連絡ください.
(3)「協会会員」は,日本溶接協会本部団体会員となります。「後援会員」は,本シンポジウムの後援団体及び日本溶接協会指定機関の会員となります.
(4)申込確定後に届く“受講確定メール”には,受講番号,受講料お振込先,請求書・領収書等ご依頼の情報についてご案内します.
・受講料のお支払いはお振込みに限ります.
・原則として銀行口座への振込をもって領収に代えさせて頂きます.
・請求書やその他ご要望がある場合は,申込時の摘要欄にご記載頂くかメールでご連絡下さい.
(5)WEB受講者には,直前にWEB会議室情報(接続テスト情報含む)をご登録のメールへお知らせします.WEB会議システムはZoomを使用します.
(6)資料については,すべての受講者に対して事前に配布できるようご案内します.資料はパスワード付きPDF(印刷不可)を配布予定です.なお,現地受講者には同資料を刷り出し配布します.一部、配布を行わない講演もございます.
(7)次の事項を遵守していただきます.
注意事項
1. WEB受講するときは,
・事務局から送付する招待メールに記されたURL等の参加者限定情報を第三者に伝えません.
・参加者以外に講演を視聴させることや参加者以外が講演を視聴可能な状態にしません.
・複数台のPC等で入室しません.
・WEB会議室に入室された受講者の名称が確認できない場合に,当日お知らせいただきますが,お尋ねに応じない場合は,会議室の外へ移動されます.
2. 現地受講する場合で,ご体調のすぐれないときは,聴講をお断りすることがございます.
3. 本シンポジウムの運営に支障をきたす行為が発覚した場合,本シンポジウムを中断,強制的に停止又は終了,WEB受講の場合はWEB会議室の外へ移動されることがあります.
4. 本シンポジウムに係る一切のデータについては,複写,記録,保存及び再配布しません.
5. 本シンポジウムの主催者からの指示があれば従います.
6. 申込確定後、受講料をお支払いいただきます.
※振込後の受講料は返却致しません。欠席の場合は,代理出席をお願い致します.
(8)現地参加の受講者向けにwi-fiは提供しておりません.
(9)ご昼食は各自ご用意下さい.
(10)当委員会は当協会の最新の新型コロナウイルス感染防止のためのガイドラインに従います.
受講者のマスク着用は任意といたします.
(11)本シンポジウムは,やむを得ない事情により運営上の変更等がある可能性がございます.
(12)ご記載いただいた個人情報は「個人情報保護に関する法律」に則り,一般社団法人日本溶接協会が定めた個人情報保護方針に従って管理いたします.詳細は別にお尋ね下さい.
以上