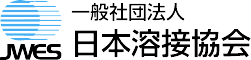2024年度事業報告
1.本部会
2024年度の部会総会を2024年5月28日に開催し、2023年度の部会事業報告および決算報告の承認ならびに、2024年度の事業計画(案)および予算(案)の審議・承認を行った。
2.技術委員会および分科会
2024年度は、5つの分科会活動と1つの共同研究WG活動に取り組んだ。技術委員会を4回開催し、各分科会および共同研究WGの活動状況報告および審議を行った。また、10月の地方開催では、IHI呉事業所 呉第二工場の見学を行った。
2.1 溶接材料の国際規格適正化調査研究(調査第1分科会:継続)
2024年度は、分科会を4回開催し、ISO規格の定期見直し及び改訂案に対する意見のとりまとめ、「JIS Z 3211 軟鋼,高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒」を対象としたJIS定期見直しを行い、対応国際規格であるISO 2560及びISO 18275に整合させたJIS改正素案を作成し、日本規格協会への公募区分B(2025年2月応募)に応募した。今後、原案作成委員会において7月から原案審議を行い、2026年2月に完成版を提出する予定で進めることとした。
2.2 調査第2分科会(AM用ワイヤに関する検討:新規)
2024年度は、キックオフとなる分科会を1回開催し、活動の主旨説明とAM部会の活動状況、WAAMに関する欧州での取組み、過去に実施した関連文献調査結果などの共有を行った。今後、対象とする素材の候補を絞り、有用なデータを取得するためのアイディア出しなどを行い、活動を具体化していくこととした。
2.3 調査第3分科会(業種別に見た各種溶接材料と将来に関する調査:新規)
2015年の市場調査から約9年が経過している。この間、溶接にまつわる市場動向は大きく変化しており、溶接材料や溶接機器、溶接技術に対する要求も変化している。本分科会では、これら至近の需要動向を明らかにすることを目的として2024年度から活動を開始した。
2024年度は、分科会を3回開催し、調査分野や対象、調査項目、集約の方法(今回は新たにFormsの利用を検討)などを具体的に決定し、2026年3月までに完成、提出することを目標とした。
2.4 調査第6分科会(アジアにおける溶接材料共通規格の検討:継続)
2024年度は、分科会を2回開催し、AWF標準化委員会の準備、出席報告および活動計画の検討を行った。
AWF標準化委員会が、4月(大阪)と11月(マレーシア)に開催され、日本からはISO、IIW、JISの標準化に関する情報共有化が行われた。また、シンガポールから国家規格開発プロセスに関するプレゼンが行われた。
大阪開催では、中国Liu氏(CWS)から提案されたTechnical Specification sub-committee(技術仕様書分科委員会)の設立がGoverning Councilで決定し、同氏が議長として関わることになった。また、マレーシア開催では、シンガポールSze氏よりAWF標準化委員会にて再度各AWFメンバー各国の産業別適用規格調査の実施について、運営評議会(Governing council)で提案がなされ、了承された。
2.5 規格化第9分科会(溶接材料のISO、JISおよびWESへの対応:継続)
本分科会は日本溶接会議(JIW)第Ⅱ委員会との合同会議体として運営し、JISの定期見直しの他、ISOおよびIIWにおける国際標準化活動への対応も行っている。2024年度は、下記4つのWGを設け、ISO規格の制改訂状況のフォローとJIS改正準備に注力した。
2.5.1 WG1:ISO全般への対応(継続)
ISO規格の新規制定および改訂事案の経過フォローのために、ISO/TC 44/SC 3(2024年6月、10月)、及びIIW(年次大会2024年7月)に出席し、技術委員会及び規格委員会において情報の共有化を図った。
ISO規格の制改訂(含定期見直し)について日本の意見を集約し、改訂案に対する日本のコメントを調査第1分科会および本WGから回答し、規格案の改善に寄与した。
2.5.2 WG 2(JISおよびWES改正への対応:継続)
日本規格協会から、溶接材料に関するJIS 9件についての定期見直し依頼があった。JIS Z 3251、JIS Z3335については「暫定確認」、他の7件を「確認」と回答した。 WES定期見直しについては、本年度の対象4件について審議し、確認と回答した。
2.5.3 WG 4(溶着金属のトランス・バレストレイン試験方法:継続)
共研第4分科会で検討した溶接関連割れ試験方法の規格化検討の活動をベースに、「トランス・バレストレイン試験方法」のWES原案に関する審議を4回行い、規格・解説案を作成した。
2.5.3 WG 5(JIS Z 3224 の改正原案作成:新規)
JIS Z 3224:ニッケル及びニッケル合金被覆アーク溶接棒の改正に向け、JIS改正原案(本文・附属書・解説)の作成、原案作成委員会のコメントに対応する審議を実施した。第3回原案作成委員会(7/16)原案の最終承認を得て、JSAへ提出を完了した。
2.6 化学機械溶接研究委員会との共同研究WG(配管溶接におけるN2バックシールド適用性の評価:継続)
2024年度は、3回開催してガイドラインに記載する項目と執筆担当者を決め、執筆を開始した。2025年度前半には、ある程度の形にまとめる方向で進めることとした。
3.関係専門部会・研究委員会および関連団体との連携
以下の委員派遣を行い、運営への参画および技術委員会での情報共有化を図った。
3.1 (一社)日本溶接協会 規格委員会
斉藤洋ISO連絡委員/規格化第9分科会WG1主査が出席し、規格委員会の運営に参画した。
3.2 (一社)日本溶接協会 電気溶接機部会 技術委員会 アーク溶接機小委員会
横田技術委員会幹事長が連絡委員として出席し、情報の共有化を図った。
3.3 (一社)日本溶接協会 JPVRC施工部会
志村技術委員会副幹事長が連絡委員として出席し、情報の共有化を図った。
3.4 (一社)日本高圧力技術協会 日本圧力容器研究会議(JPVRC)運営委員会
志村技術委員会副幹事長が連絡委員として出席し、情報の共有化を図った。
3.5 (一社)日本溶接協会 安全衛生・環境委員会
澤口委員と齋藤委員が連絡委員として出席し、情報の共有化を図った。
3.6 (一社)日本溶接協会 AM部会 技術委員会
伊藤技術委員長が連絡委員として出席し、情報の共有化を図った。
3.7 (一社)日本鋼構造協会 建築鉄骨溶接部の機械的性質の標準試験マニュアル改正小委員会
栗山委員が連絡委員として出席し、運営への参画および情報の共有化を図った。
4.出版物の発刊
2023年度の技術委員会および分科会の活動成果をまとめて「溶接の研究」No.63(PDF版)を作成した。