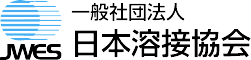2024年度事業報告
1. 本部会
建設部会はゼネコン、鉄骨・橋梁のファブリケーター、溶接材料メーカ等を会員とし、中立機関を含めて13会員で構成している。2024年度の部会は、対面+Web会議にて計3回開催された。内容を以下に報告する。
1.1 討議及び研究
(1) 過大ルート間隔の処理方法の研究 [2025年3月24日]
鉄骨の現場溶接における過大ルート間隔処理方法について、一般的な処理方法のバタリング以外に品質確保ができ工程短縮となる工法の研究を行っている。試験の結果、ルート間隔15mm の場合、入熱量40kJ/cm 以下、パス間温度350℃以下とし、初層と2 層目を1 パスで溶接した場合は、標準のルート間隔7mm と比較して30%程度収縮量が増加するが、初層を2 パスに分割した場合は15%程度の増加となることが確認できた。また、パス間温度管理を150℃以下とした場合は5%程度であり、ルート間隔7mmと同等の収縮量であった。各ケースとも収縮量は1.5mm以内であり,板厚25mm 程度では入熱量40kJ/cm、パス間温度350℃以下の管理の溶接で問題ないと考えられる。また、板厚や構造的重要度などを考慮する場合は、初層と2 層目を1層2パスに、さらにパス間温度管理を厳格化して溶接することが考えられる。
1.2 技術講演 [2025年3月24日]
当部会では、溶接に関連するDXやカーボンニュートラルについて検討していくこととしており、下記の2件の技術講演を行った。
(1) パナソニックのカーボンニュートラルへの取り組み
「Panasonic GREEN IMPACT」として、2050年にむけて現時点の全世界CO₂総排出量の約1%にあたる3億ton以上の削減インパクトを目指している。溶接機の消費電力削減として、被覆アーク溶接の直流溶接機への移行、マグ溶接のサイリスタ溶接機やインバーター溶接機からデジタル溶接機に移行がある。被覆アーク溶接の直流溶接機は、感電事故のリスク低減にもなる。溶接ロボットでは、アクティブワイヤ溶接法により消費電力削減や効率化が図れる。DXの活用として,CO2/MAG溶接機の稼働や溶接情報等をiWNBで一元管理し、進捗や品質の見える可による生産性・品質向上について取り組んでいる。
(2) レーザ超音波法による非破壊・非接触検査
レーザ超音波法は,パルス幅が数nsの送信レーザを金属材料に照射して表面から数十mm程度の層をプラズマ化し,照射点を音源とした超音波を発生させ,この超音波が欠陥で反射し,受信レーザを照射して超音波による微小な表面振動を検出する方法である。レーザ超音波法は,非接触で溶接部の内部きず検査や亀裂調査が可能な検査方法であり,この方法による溶接インプロセス検査装置が導入されている例があり,今後,装置の小型化を目指しており,建築鉄骨や橋梁等の鋼構造物への適用に期待できる。
1.3 溶接協会内委員会への委員派遣
本年度は、下記2委員会へ委員派遣を行った。
・規格委員会
・安全衛生・環境委員会
2. 建築鉄骨の若手技能者・技術者向けの講習会 [2024年12月16日]
昨年度からテキスト作成WGを設置し、建築鉄骨の若手技能者・技術者向けの講習会を検討し、講習会テキストを作成した。講習会は、「建築鉄骨の溶接の勘所」のタイトルで12月16日に開催し、受講者は80名であった。プログラムは、①溶接の基礎知識、②工場溶接、③鉄骨工事における工事現場溶接、④溶接部の品質管理・検査とし、品質管理や品質保証に必要な基礎知識だけでなく,最新の工場溶接や現場溶接の技術についても説明した。この講習会のきっかけに、溶接管理技術者の資格制度にチャレンジする技能者・技術者が増えることを期待したい。なお、本講習会は継続的に開催する予定である。